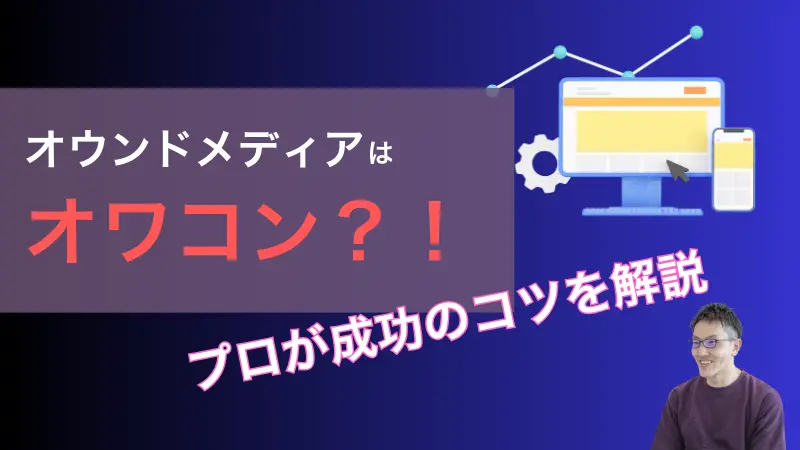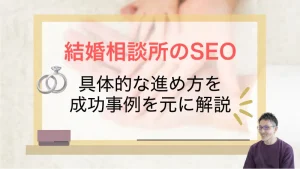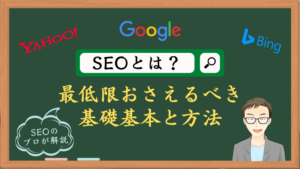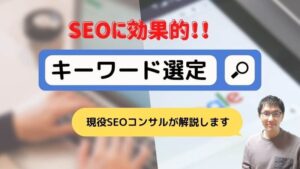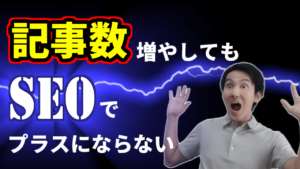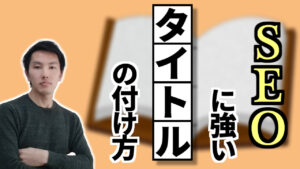SEO初心者
SEO初心者「オウンドメディア、頑張って始めたはいいけど、本当に意味あるのかな…」
「『オワコン』なんて声も聞くし、なんだか不安だなぁ」
もしかして、今あなたはそのような風に感じていませんか?
時間もコストもかけているのに、なかなか成果が見えてこないと、続けるモチベーションを保つのも大変ですよね。
「このまま続けて大丈夫なんだろうか…」と、もどかしく感じてしまう気持ち、僕も非常によく分かります。
実際に、クライアント様からも同じような悩みを打ち明けられることは少なくありません。
でも、ちょっと待ってください。
そのオウンドメディア、諦めてしまうのはまだ早いかもしれません。
この記事を読めば、「オワコン」といわれる具体的な理由を冷静に理解した上で、それでもオウンドメディアが持つ「本当の価値」と、失敗せずに成果を出すための「具体的なポイント」が、きっとクリアに見えてきます。
この記事では、オウンドメディアがなぜ「オワコン」といわれがちなのか、その背景にある5つの理由から解説します。
そして、それに負けないオウンドメディアの魅力と価値、さらに皆さんのメディアをオワコンにさせないための、僕が実践で培ってきた11個の重要ポイントまで、詳しく見ていきましょう。
- なぜ「オワコン」といわれるのか? その5つの理由
- それでもオウンドメディアを続けるべき本当の価値
- 失敗しない!オウンドメディア成功のための11個の秘訣
この記事を読み終えるころには、「オワコン」という言葉に振り回されることなく、自信を持ってオウンドメディア運営の舵取りができるようになっているはず。
あなたのオウンドメディアが、会社の未来を照らす、かけがえのない資産になるでしょう。
そのような未来を一緒に目指しましょう。
オウンドメディアが今オワコンといわれる5つの理由
「オウンドメディアはオワコンだ」なんて声、耳にしますよね。
たしかに、以前のようなブームは落ち着いたかもしれません。
それでは、なぜそのようにいわれるようになったのでしょうか?
それには、いくつかの理由が考えられます。
ここでは、主な5つの理由をひとつずつ見ていきましょう。
ネット上に情報が溢れてきている
まず1つ目の理由は、シンプルに「情報が多すぎる」ことです。
今や、知りたいことがあれば、検索すれば山ほど情報が出てきますよね。
企業だけでなく個人も気軽に情報発信できるようになった結果、インターネット上はまさに情報の大洪水状態。
質が高い情報もあれば、残念ながらそうでない情報も玉石混交です。
このような状況だと、ユーザーはどの情報を信じればよいか迷ってしまいます。
そして、企業側からすると、一生懸命作ったコンテンツも、無数の情報の中に埋もれてしまい、読んでもらえない…なんてことが起こりやすくなっています。
せっかく時間をかけて作ったのに、誰にも届かないのは悲しいですよね。
- 情報量が多すぎて、自社のコンテンツが埋もれてしまう
- ユーザーが情報の取捨選択に疲れてしまう
- 質の低い情報も多く、信頼できる情報源を見つけるのが難しい
後発でオウンドメディアを始めても、すでに存在する膨大な情報の中で存在感を示すのは、以前よりも格段に難しくなっているといえます。
だからこそ、「今から始めても遅い」「オワコンだ」と感じてしまう方がいるのも、無理はないのかもしれません。
SEOの難易度が年々上がっている
オウンドメディア集客の柱といえば、やはりSEOですよね。
しかし、このSEOが年々難しくなっていることも、「オワコン説」の一因といえます。
Googleのアルゴリズムは、ユーザーにとってより有益な情報を提供するために、日々進化しています。
特に近年重要視されているのが「E-E-A-T」という考え方です。
E-E-A-Tとは?
Experience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼性)の頭文字を取ったもの。
Googleがコンテンツの品質を評価する上で重視する指標です。
特に、YMYL(Your Money or Your Life:お金や人生に大きな影響を与える情報)の分野では、このE-E-A-Tが非常に厳しく評価されます。
つまり、検索上位を狙うには、ただキーワードを詰め込んだ記事ではなく、実際の経験に基づいた、専門的で、権威があり、信頼できる情報を提供する必要があるわけです。
これは、付け焼き刃の知識では太刀打ちできません。
専門家への取材や監修など、コンテンツ制作にかかる手間やコストも、以前に比べると格段に上がっています。
このハードルの高さが、「もうSEOで上位表示させるのは無理だ…」と感じさせてしまう一因になっているわけです。
たしかに難易度は上がっていますが、裏を返せば、ユーザーにとって本当に価値ある情報を提供できれば、Googleからもしっかり評価されるということ。
小手先のテクニックではなく、コンテンツの本質が問われる時代になったといえます。
SNSなど多様な情報発信チャネルが増えている
X(旧Twitter)やInstagram、Facebook、YouTube、TikTok…。
今や、企業がユーザーと接点を持つためのチャネルは、オウンドメディア以外にもたくさんありますよね。
特にSNSは、情報の拡散力が高く、ユーザーと直接コミュニケーションを取りやすいのが魅力です。
手軽に始められることもあり、「わざわざ手間のかかるオウンドメディアをやらなくても、SNSで十分じゃないか」と考える企業が増えるのも自然な流れかもしれません。
たしかに、SNSには即時性や拡散力といったメリットがあります。
しかし、SNSの情報はフロー型(流れ去っていく情報)であるのに対し、オウンドメディアはストック型(蓄積されていく資産)という違いがあります。
| チャネル | 情報の性質 | 主なメリット | 主なデメリット |
|---|---|---|---|
| オウンドメディア | ストック型 | 資産性、深い情報提供、ブランディング | 成果まで時間がかかる、運用負荷 |
| SNS | フロー型 | 拡散力、即時性、コミュニケーション | 情報が流れやすい、炎上リスク |
| Web広告 | フロー型 | 即効性、ターゲティング | 継続的なコスト、広告感 |
このように、それぞれに得意なこと、不得意なことがあります。
SNSが台頭したからといって、オウンドメディアの価値が完全になくなったわけではありません。
大切なのは、それぞれの特性を理解し、目的に合わせて使い分けることです。
「オウンドメディアかSNSか」の二者択一ではなく、うまく連携させていく視点が重要になります。
オウンドメディアは成果が出るまで時間がかかる
オウンドメディアの運用は、残念ながら、始めてすぐに目に見える成果が出るものではありません。
コツコツと質の高いコンテンツを作り続け、SEOで評価されるようになるまでには、早くても数ヶ月、場合によっては1年以上かかることも珍しくないです。
まるで、じっくり時間をかけて育てる植物みたいですよね。
さらに、その成果を正確に測るのが難しい、という側面もあります。
PV数や検索順位だけでなく、ブランディングへの貢献度や、見込み客の質の変化など、測りにくい指標も多いんです。
これが、「本当に効果があるのか?」という疑念につながりやすいです。
- SEO効果が出るまでに時間がかかる(数ヶ月~1年以上)
- 効果測定が難しい(PV数以外の価値が見えにくい)
- 短期的な売上目標達成には向かないケースがある
特に、すぐに売上につながるような短期的な成果を求められる状況だと、「オウンドメディアは時間がかかりすぎる」「費用対効果が悪い」と判断されがちです。
この「時間のかかり具合」と「成果の見えにくさ」が、担当者のモチベーションを削いだり、経営層からの理解を得られにくくしたりして、「オワコン」といわれる一因になっていると感じます。
運用リソースの確保が難しい
質の高いオウンドメディアを継続的に運営するには、想像以上に多くのリソースが必要です。
企画、取材、執筆、編集、デザイン、SEO、効果測定、改善…。
これら全てを高いレベルでこなしていくには、専門的なスキルを持った人材と、十分な時間、そして予算が欠かせません。
正直、片手間でできるような簡単なことではありません。
特に中小企業の場合、専任の担当者を置くのが難しかったり、他の業務と兼任していたりするケースが多いのではないでしょうか。
そうなると、どうしても更新が滞りがちになったり、コンテンツの質が低下したりしてしまいます。
- 企画・戦略立案:誰に何を伝え、どうなってもらうか
- コンテンツ制作:取材、執筆、編集、校正、画像・動画作成
- SEO:キーワード調査、内部施策、外部施策
- サイト管理:CMS運用、デザイン調整、セキュリティ対策
- 効果測定・分析:アクセス解析、レポート作成、改善提案
- プロモーション:SNS連携、広告出稿など
このように、やるべきことは多岐にわたります。
これらのリソースを継続的に確保できないまま始めてしまい、途中で挫折してしまうケースが後を絶ちません。
「結局、続けられないじゃないか」という経験が、「オウンドメディアなんてオワコンだ」という諦めの声につながっている側面もあると感じます。
始める前の計画と覚悟が、非常に重要になるのです。
オワコンではない!オウンドメディアを運用する本当の価値
ここまで「オワコン」といわれる理由を見てきましたが、それでも僕は、オウンドメディアには計りしれない価値がある、と確信しています。
短期的な視点だけで見るとデメリットに思えることも、長期的な視点で見れば大きなメリットに変わるんです。
ここでは、厳しい状況の中でもオウンドメディアを運用し続ける「本当の価値」について見ていきましょう。
きっと、「やっぱりオウンドメディアってすごい!」と感じてもらえるはずです。
コンテンツの資産化により長期的な集客が見込める
オウンドメディア最大の魅力は、なんといってもコンテンツが「資産」になることです。
Web広告は出稿をやめれば効果がなくなりますし、SNSの投稿も基本的には流れていってしまいますよね。
でも、オウンドメディアに掲載した質の高い記事は、公開後もずっと、あなたの代わりに働き続けてくれるんです。
まるで、インターネット上に自動販売機を設置するようなイメージでしょうか。
一度検索エンジンに評価されれば、その記事は長期間にわたってユーザーを呼び込み続けてくれます。
時間が経つほどコンテンツは蓄積され、サイト全体の評価も高まり、安定した集客チャネルへと成長していく。
これは、他のメディアではなかなか得られない、オウンドメディアならではの大きなメリットです。
- 一度作れば、コンテンツが継続的に集客してくれる
- 時間が経つほどコンテンツが蓄積され、サイト価値が向上する
- 広告費に頼らない、安定した集客基盤を構築できる
最初は大変かもしれませんが、コツコツ続けた先には、広告費をかけなくても集客できる、という素晴らしい未来が待っています。
この「資産性」こそが、短期的な視点だけでは見えない、オウンドメディアの真の価値といえるでしょう。
長期的に見れば、これほど費用対効果の高い施策はない、と僕は考えています。
オウンドメディアだけでなく作ったコンテンツを横展開できる
オウンドメディアのために作ったコンテンツって、実はオウンドメディアの中だけで完結させるのはもったいないんです。
せっかく時間と労力をかけて作ったのだから、様々な形で「横展開」しましょう。
ひとつのコンテンツを、様々なチャネルで活用することで、より多くの人に届けられますし、コンテンツ制作の効率もぐっと上がります。
まさに一石二鳥、いや三鳥くらいの価値があるんですよ。
例えば、オウンドメディアに公開したブログ記事の要点をまとめて、X(旧Twitter)で発信する。
記事の内容を元に、分かりやすい図解やインフォグラフィックを作成してInstagramで共有する。
さらに、記事の内容を深掘りした解説動画をYouTubeで公開する、なんてことも可能です。
- X(旧Twitter): 記事の要約、ポイント抜粋、更新通知
- Instagram/Facebook: 図解、インフォグラフィック、関連性の高い画像と共に紹介
- YouTube: 記事内容の解説動画、対談形式での深掘り
- メールマガジン: 記事のダイジェスト、限定情報と合わせた配信
- セミナー/ウェビナー: 記事内容を元にした講演資料作成
- 営業資料: 記事コンテンツの一部を引用、補足資料として活用
このように、オウンドメディアはコンテンツを生み出す「源泉」となり、そこから様々なチャネルへと展開していくことが可能です。
それぞれのチャネルの特性に合わせて情報を加工・発信することで、ユーザーとの接点を最大化できる。
コンテンツを使い捨てにせず、多角的に活用する視点を持つことが、オウンドメディア運営をより豊かにする秘訣です。



このcotrotブログの中でも、一部のSEO記事は以前YouTubeで解説したものをわかりやすく文章で解説するなど、コンテンツを横展開させています。
オウンドメディアが企業のブランディングにつながる
オウンドメディアは、単なる情報発信ツールではありません。
企業の考え方や価値観、専門性を伝え、読者との間に信頼関係を築くための、強力なブランディングツールにもなり得るんです。
継続的に質の高い、そして独自性のある情報を発信し続けることで、「この分野なら、あの会社のメディアだよね」と認知されるようになります。
これは、広告だけではなかなか築けない、深いレベルでのブランドイメージ構築につながります。
例えば、専門的なノウハウや業界の最新動向、あるいは自社の取り組みや働く人の想いなどを発信する例を考えてみましょう。
読者はその企業に対して「専門性が高い」「信頼できる」「共感できる」といったポジティブな印象を抱くようになります。



僕が運営しているこのcotrotブログも、SEOやWeb集客に関する僕自身の知識や経験を発信することで、「SEOならミツキさんに相談してみようかな」と思っていただけるきっかけになれば嬉しいな、という想いで続けています。
| 発信する情報 | 期待される印象 |
|---|---|
| 専門知識・ノウハウ | 専門性が高い、頼りになる |
| 業界トレンド・考察 | 先進的、視野が広い |
| 課題解決事例 | 実績がある、信頼できる |
| 企業の理念・文化 | 共感できる、応援したい |
| 働く人の声 | 親近感が湧く、雰囲気がよい |
このように、オウンドメディアを通じて一貫したメッセージを発信し続けることは、価格競争に陥らない、独自のブランド価値を確立するための重要なステップとなるんです。
ファンを作り、長期的な関係性を築く上で、オウンドメディアの役割は非常に大きいといえますね。
質の高い見込み客の創出につなげやすい
オウンドメディアの価値は、ただアクセス数を集めるだけではありません。
本当に価値があるのは、自社の製品やサービスに関心を持ってくれる可能性の高い、「質の高い見込み客」を集めやすい、という点です。
なぜなら、ユーザーは自ら特定のキーワードで検索し、課題解決や情報収集のためにオウンドメディアを訪れるからです。
つまり、もともと関心度が高い状態で接触してくれるわけですね。
これは嬉しいポイントです。
例えば、「〇〇 使い方」「〇〇 比較」「〇〇 選び方」といったキーワードで検索して記事にたどり着いたユーザーは、その製品やサービスに対する課題意識や興味が明確です。
そのようなユーザーに対して、記事の中で解決策を提示したり、関連する自社サービスを紹介したりすることで、自然な流れで問い合わせや資料請求といったアクションにつなげやすくなります。
- 課題やニーズが明確なユーザーが集まりやすい
- コンテンツを通じて、自然な形で自社サービスを認知してもらえる
- 信頼関係が構築された状態で、次のアクション(問い合わせなど)につながりやすい
- 広告に比べて、押し付け感がなく受け入れられやすい
闇雲に広告を打つよりも、オウンドメディアでじっくりと情報提供し、信頼関係を築いた上でアプローチする方が、結果的に成約率の高い、質の高いリードを獲得できる可能性が高いんです。
短期的な効果は見えにくいかもしれませんが、長期的に見れば、営業活動の効率化にも大きく貢献してくれる存在といえるでしょう。
オウンドメディアをオワコン化しないための11個のポイント
さて、オウンドメディアがオワコンではない理由、そしてその価値についてお話ししてきました。
とはいえ、闇雲に運営していても成果は出ません。
「オワコン化」させずに、しっかりと価値あるメディアへと育てていくためには、押さえておくべき重要なポイントがいくつかあります。
ここでは、僕がこれまでの経験で特に重要だと感じている11個のポイントを、ひとつずつ丁寧に解説していきますね。
これらを意識するだけで、あなたのオウンドメディアはきっと変わります。
【最重要】目的を明確化し、KPIを設定する
これが全ての土台であり、最も重要だといっても過言ではありません。
あなたのオウンドメディアは、「何のために」存在するのでしょうか?
最終的に達成したいゴール(KGI: Key Goal Indicator)と、その達成度を測るための中間指標(KPI: Key Performance Indicator)を、具体的に設定することが不可欠です。
ここが曖昧だと、行く先を決めずに新幹線に乗り込むことと同じような状況になってしまいます。
目的が明確になれば、どのようなコンテンツを作るべきか、どのような指標を追うべきか、おのずと方向性が定まります。
例えば、「新規リード獲得」が目的なら、KPIは「問い合わせ数」「資料ダウンロード数」などになりますし、「ブランディング向上」が目的なら、「指名検索数」「記事のSNSシェア数」などを追うことになるでしょう。
例:新規リード獲得、ブランド認知度向上、採用応募者数増加、顧客満足度向上など
例:PV数、セッション数、検索順位、問い合わせ数、資料DL数、指名検索数、SNSシェア数、記事読了率など
この目的とKPIは、関係者全員で共有し、定期的に見直すことが大切です。
最初にしっかりと羅針盤を設定しておくこと。
これが、オウンドメディアという長い航海を成功させるための、何よりも重要な第一歩となるのです。
ターゲットとしたい読者のペルソナ像を明確にする
目的が決まったら、次は「誰に」情報を届けたいのかを具体的に考えます。
いわゆる「ペルソナ設定」ですね。
漠然と「多くの人に読んでほしい」と考えるのではなく、年齢、性別、職業、役職、抱えている悩み、情報収集の方法など、架空の読者像を詳細に設定するんです。
これが意外と、コンテンツ作りの精度を上げるのに役立つんですよ。
ペルソナが明確になると、その人が本当に知りたい情報は何なのか、どのような言葉遣いや表現が響くのか、どのようなデザインが見やすいのか、といったことが具体的にイメージしやすくなります。
例えば、ITに詳しくない中小企業の経営者向けなら専門用語を避け、具体的な事例を多く盛り込む、といった工夫ができますよね。
- 基本情報:年齢、性別、居住地、職業、役職、年収、家族構成
- 価値観・ライフスタイル:性格、趣味、休日の過ごし方
- 仕事上の役割・目標:担当業務、目標、課題、悩み
- 情報収集の方法:よく見るWebサイト、SNS、情報源
- ITリテラシー:PCスキル、Webサービスの利用頻度
たったひとりの「理想の読者」に向けて書く意識を持つことで、結果的に多くの人の心に響くコンテンツを作れるようになります。
誰に届けたいのかを明確にすること。
これが、読者の心をつかむコンテンツ作りの秘訣です。
オウンドメディアのコンセプト(軸)を定める
目的とターゲットが決まったら、次はそのオウンドメディアが持つ独自の「コンセプト」を定めましょう。
コンセプトとは、そのメディアが「どのような価値を提供し、他とどう違うのか」を示す、いわばメディアの「軸」となる考え方です。
これがしっかり定まっていると、発信する情報に一貫性が生まれ、メディアとしての個性や魅力が際立ちます。
なんだかワクワクしてきませんか?
コンセプトを定める際には、「誰に」「何を伝え」「どうなってほしいか」を改めて考え、それを端的な言葉で表現してみるとよいでしょう。
例えば、「Webマーケティング担当者の悩みを解決し、自信を持って施策を実行できるようになるメディア」とか、「丁寧な暮らしを楽しむための、ちょっとしたヒントと出会えるメディア」といった具合です。
- 提供価値:読者にどのようなメリットや解決策を提供するか?
- 独自性:競合メディアと比べて、どこが違うのか? 強みは何か?
- トーン&マナー:どのような雰囲気、言葉遣いで情報を発信するか?
- 目指す世界観:このメディアを通じて、どのような世界を実現したいか?
コンセプトが明確であれば、コンテンツの企画やデザイン、タイトル決めなど、あらゆる場面で判断基準となります。
発信する情報にブレがなくなり、読者にも「このメディアらしさ」が伝わりやすくなるはずです。
流行に流されず、独自の価値を提供し続けるためにも、しっかりとしたコンセプト設定は欠かせません。
ペルソナが求めるコンテンツを想像する
目的、ターゲット、コンセプトが決まったら、いよいよコンテンツの中身を考えていきます。
ここで重要なのは、設定したペルソナ(ターゲット読者)が、「本当に知りたいこと」「悩んでいること」「解決したいこと」は何かを、徹底的に想像することです。
企業側が「伝えたいこと」だけを発信するのではなく、あくまで読者の視点に立って企画を練ることが重要になってきます。
これが、読まれるコンテンツを作るための大原則です。
ペルソナがどのようなキーワードで検索するかを想像してみましょう。
サジェストキーワードツールやQ&Aサイトなどを活用するのも有効です。
また、営業担当者やカスタマーサポートなど、普段から顧客と接している部署からヒアリングするのも、リアルなニーズを知る上で非常に役立ちます。
まさに、宝の山が眠っているかもしれません。
- キーワード調査:Googleキーワードプランナー、ラッコキーワード、Ubersuggestなど
- Q&Aサイト分析:Yahoo!知恵袋、教えて!gooなどで関連する質問を調査
- SNS分析:X(旧Twitter)などで関連キーワードの投稿を調査
- 社内ヒアリング:営業、カスタマーサポート、開発担当者などから顧客の声を収集
- 既存顧客アンケート:直接顧客に悩みや関心事を質問
ペルソナの悩みや疑問に寄り添い、「そうそう、これが知りたかったんだ!」と思ってもらえるようなコンテンツを提供すること。
そのためには、表面的な情報だけでなく、一歩踏み込んだ専門的な解説や、具体的な解決策、あるいは共感を呼ぶようなストーリーが求められます。
読者の心を動かすコンテンツ作りを目指しましょう。
読者が求めるものとコンバージョンにつながる間を狙う
読者が求める情報を提供するのは大前提ですが、企業としてオウンドメディアを運営する以上、最終的には何らかの成果(コンバージョン)につなげたいですよね。
問い合わせ、資料請求、商品購入、セミナー申し込みなど、設定した目的に応じたゴールがあるはずです。
ここで重要になるのが、「読者が求める情報」と「企業が達成したいコンバージョン」の、ちょうどよいバランスを見つけることです。
これがなかなか難しいのですが、腕の見せどころでもあります。
読者の疑問や悩みに応える有益な情報を提供しつつ、その解決策として自社の製品やサービスが役立つことを、自然な流れで示唆する。
決して押し売りになるのではなく、「この記事を読んで課題が解決できそうだけど、もっと詳しく知りたいな」「この会社なら信頼できそうだ」と感じてもらい、次のアクションへとスムーズに誘導するイメージです。
| コンテンツ内容 | 自然な誘導先(コンバージョン) |
|---|---|
| 〇〇の選び方ガイド | 関連製品の紹介ページ、比較シミュレーション |
| 課題解決のノウハウ記事 | 関連ソリューションの資料ダウンロード、無料相談 |
| 導入事例インタビュー | 問い合わせフォーム、サービス詳細ページ |
| 業界トレンド解説 | 関連セミナー・ウェビナーの案内 |
読者の満足度を高めながら、ビジネス上の成果にもつなげる。
この絶妙なバランス感覚が、オウンドメディアを成功させる上で非常に重要になります。
記事の最後に関連情報へのリンクを設置したり、CTA(Call to Action)ボタンを適切に配置したりといった工夫も効果的ですね。
あくまで読者ファーストで自社の利益ばかりを追い求めない
前のポイントとも関連しますが、必ず忘れてはいけないのが「読者ファースト」の精神です。
コンバージョンを意識するあまり、自社の商品やサービスの宣伝ばかりになってしまうと、読者はすぐに離れていってしまいます。
「また広告か…」と思われたら、もう読んでもらえませんよね。
これは、僕も常に自戒している点です。
大切なのは、まず読者の悩みや疑問に真摯に向き合い、価値ある情報を提供すること。
その上で、もし自社の製品やサービスがその解決に役立つのであれば、控えめに、そして自然な形で紹介する、というスタンスが大事です。
読者が「この記事、役に立ったな」「この会社、信頼できそうだな」と感じてくれれば、結果的に自社への関心も高まり、コンバージョンにつながる可能性が出てきます。
- 宣伝色を抑える:記事全体に対する宣伝の割合を低く保つ
- 客観的な情報提供:メリットだけでなく、デメリットや注意点も正直に伝える
- 解決策の提示:自社製品が唯一の解決策であるかのような表現は避ける
- 読者の疑問に答える:想定される質問には先回りして回答を用意する
短期的な利益を追い求めるのではなく、長期的な視点で読者との信頼関係を築くこと。
その誠実な姿勢こそが、最終的にオウンドメディアを成功に導き、ひいては企業の成長にも貢献するのだと、僕は信じています。
読者のためのメディア作りを、常に心がけましょう。
多様なコンテンツ形式を活用して読者を魅了する
オウンドメディアというと、ついついテキスト中心のブログ記事ばかりをイメージしがちですが、それだけではもったいないです。
読者の興味を引きつけ、より深く情報を理解してもらうためには、様々なコンテンツ形式を積極的に活用することが効果的です。
テキストだけでなく、画像や図解、動画などを組み合わせることで、コンテンツはさらに魅力的になります。
このちょっとした工夫で、読者の満足度は大きく変わります。
- 例えば、複雑なデータはインフォグラフィックで見やすく表現する。
- 製品の使い方やサービスのデモンストレーションは動画で見せる。
- お客様の成功事例は、インタビュー記事や動画でリアルな声を届ける。
テキストでは伝えきれないニュアンスや臨場感を、他の形式で補うことで、コンテンツの価値は格段に高まります。
- インフォグラフィック:データや統計情報を分かりやすく可視化
- 図解・イラスト:複雑な仕組みや手順をシンプルに表現
- 動画:製品デモ、使い方解説、インタビュー、セミナー映像など
- 事例紹介:顧客の声、具体的な成果をストーリーで紹介
- チェックリスト・テンプレート:読者がすぐに行動に移せる実践的なツール
- 診断コンテンツ:読者の状況に合わせてパーソナライズされた情報提供
もちろん、全ての記事で多様な形式を使う必要はありません。
コンテンツの内容やターゲットに合わせて、最適な形式を選択することが重要です。
テキストだけでは飽きてしまう読者も、多様な形式を組み合わせることで、最後まで興味を持って読み進めてくれる可能性が高まります。
コンテンツ表現の引き出しを増やしていきましょう。
長期的な視点で運用体制を整える
オウンドメディアは短距離走ではなく、マラソンのようなもの。
成果が出るまでには時間がかかりますし、継続することが何よりも重要です。
だからこそ、場当たり的な運用ではなく、長期的な視点に立って、無理なく続けられる運用体制を整えることが不可欠になります。
「続けること」自体が、ひとつの大きな価値になるのです。
具体的には、誰が、いつ、どのような役割で関わるのかを明確にし、コンテンツ制作のスケジュールやフローを確立することが大切です。
担当者がひとりで抱え込むのではなく、チームで協力したり、必要に応じて外部の専門家(ライター、編集者、デザイナー、SEOコンサルタントなど)の力を借りたりすることも検討しましょう。
僕のようなフリーランスも、柔軟にサポートできます。
- 役割分担の明確化:編集長、企画担当、ライター、編集者、デザイナーなど
- コンテンツカレンダー作成:公開スケジュール、担当者、進捗状況を管理
- 制作フローの確立:企画→取材→執筆→編集→校正→デザイン→公開→分析
- 予算の確保:コンテンツ制作費、ツール利用料、外注費など
- 内製と外注のバランス:自社の強みと外部リソースの活用
- 定期的なミーティング:進捗確認、課題共有、改善策の検討
安定した運用体制があれば、担当者の変更があった場合でも、メディアの品質を維持しやすくなります。
また、無理のない計画を立てることで、担当者の負担を軽減し、モチベーションを維持することにもつながります。
焦らず、着実に、長く続けられる仕組み作りを目指しましょう。
SEOに依存せず他の集客方法も狙う
オウンドメディアの集客において、SEOは非常に重要な柱です。
しかし、SEOだけに頼りすぎるのは、実はリスクも伴います。
Googleのアルゴリズム変動によって、ある日突然アクセスが激減してしまう可能性もゼロではないためです。
想像しただけでも、ちょっと怖いですよね。
だからこそ、SEO以外の集客チャネルも育てておくことが大切なのです。
例えば、SNSでの積極的な情報発信や、メールマガジンでの記事紹介、関連性の高い外部サイトからのリンク獲得(被リンク)、Web広告の活用などが考えられます。
特にSNSは、記事の更新情報を伝えたり、読者とコミュニケーションを取ったりする上で有効な手段です。
オウンドメディアとSNSを連携させることで、相乗効果も期待できます。
| チャネル | 主な役割・メリット |
|---|---|
| SNS (X, Facebook, Instagramなど) | 情報拡散、コミュニケーション、ファン作り |
| メールマガジン/ニュースレター | 既存読者への再訪促進、ナーチャリング |
| 外部サイトからの被リンク | SEO効果向上、参照トラフィック獲得 |
| Web広告(リスティング, ディスプレイ) | 即効性のある集客、潜在層へのリーチ |
| プレスリリース | メディア掲載による認知度向上 |
| セミナー/ウェビナー | 直接的なリード獲得、深い関係構築 |
複数の集客経路を持っておくことで、特定のチャネルに何か問題が起きても、メディア全体のアクセスがゼロになる事態を防げます。
リスクを分散し、安定したメディア運営を実現するためにも、SEOだけに固執せず、多角的な集客戦略を検討することが重要です。
運営者をホワイトボックス化する
誰が書いているのか分からない情報よりも、「この人が書いているんだ」と顔が見える情報の方が、なんだか信頼できませんか?
特に専門性が求められる分野では、運営者や執筆者の情報を開示すること(ホワイトボックス化)が、読者からの信頼を得る上で非常に重要になります。
これは、Googleが重視するE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の観点からも有効なアプローチです。
具体的には、記事ごとに執筆者のプロフィール(氏名、経歴、専門分野、SNSアカウントなど)を掲載したり、監修者がいる場合はその情報を明記したりします。
また、メディア全体の運営体制や編集方針を公開することも、透明性を高める上で効果的です。
読者は、「どのような人が、どのような想いで情報を発信しているのか」を知ることで、そのメディアに対する親近感や信頼感を深められます。



このcotrotブログでも、僕(ミツキ)がどのような経験を持つSEOコンサルタントなのか、プロフィールページで詳しく紹介しています。
顔が見えることで、安心して記事を読んでいただけたら嬉しいです。
- 読者からの信頼性が向上する
- E-E-A-T(特に権威性・信頼性)の向上につながる
- 執筆者のモチベーション向上にもつながる可能性がある
- メディアに個性や「らしさ」が生まれる
もちろん、プライバシーの問題など、全ての情報を公開できない場合もあるでしょう。
しかし、可能な範囲で運営者の情報をオープンにすることは、読者との良好な関係を築き、メディアの信頼性を高める上で、非常に有効な手段といえます。
隠すのではなく、見せていく姿勢が大切ですね。
ツールも活用しながらPDCAを回す
オウンドメディア運営は、「公開して終わり」ではありません。
むしろ、公開してからが本当のスタートです。
公開したコンテンツが、どれくらい読まれているのか、どのキーワードで検索されているのか、読者はどのような行動を取っているのか。
これらのデータを分析し、改善を繰り返していく「PDCAサイクル」を回すことが、メディアを成長させる鍵となります。
正直、地道な作業ですが、これが一番効くんですよね。
幸い、今はデータ分析や改善活動をサポートしてくれる便利なツールがたくさんあります。
Google Analytics(GA4)でアクセス状況を把握し、Google Search Consoleで検索パフォーマンスを確認する。
ヒートマップツールで読者の熟読箇所や離脱ポイントを分析し、SEOツールでキーワード順位や競合サイトの動向をチェックする。
これらのツールをうまく活用することで、勘や経験だけに頼らない、データに基づいた改善が可能になります。
- アクセス解析:Google Analytics (GA4)
- 検索パフォーマンス分析:Google Search Console
- ヒートマップ分析:Microsoft Clarity, ミエルカヒートマップ など
- SEO分析:GRC, Rank Tracker, Ahrefs, SEMrush など
- キーワード調査:Googleキーワードプランナー, ラッコキーワード など
Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善)のサイクルを、ツールを活用しながら回し続けること。
定期的にデータを確認し、課題を見つけ、改善策を実行し、またその結果を確認する。
この地道な繰り返しが、オウンドメディアを着実に成長させ、目標達成へと導いてくれます。
データは嘘をつきませんからね。
まとめ
今回は、「オウンドメディアはオワコンなのか?」という疑問にお答えすべく、オワコンといわれる理由から、その本当の価値、そして失敗しないための11個のポイントまで、詳しく解説してきました。
たしかに、情報過多やSEO難化、SNSの台頭など、オウンドメディアを取り巻く環境は厳しくなっています。
成果が出るまで時間もかかりますし、運用リソースの確保も大変です。
だから、「オワコン」といわれてしまう気持ちも分からなくはありません。
しかし、それでもオウンドメディアには、それを補って余りある価値があります。
- コンテンツが資産となり、長期的な集客を実現する
- 多様なチャネルへの横展開が可能
- 企業のブランディングに大きく貢献する
- 質の高い見込み客を獲得しやすい
これらの価値を最大限に引き出し、「オワコン化」させないためには、今回ご紹介した11個のポイントを意識することが重要です。
- 目的とKPIを明確にする
- ペルソナ像を明確にする
- コンセプト(軸)を定める
- ペルソナが求めるコンテンツを想像する
- 読者の求めるものとCVの間を狙う
- 読者ファーストを徹底する
- 多様なコンテンツ形式を活用する
- 長期的な視点で運用体制を整える
- SEO以外の集客も狙う
- 運営者をホワイトボックス化する
- ツールを活用しPDCAを回す
オウンドメディア運営は、決して楽な道のりではありません。
しかし、正しい戦略と地道な努力を続ければ、必ずや企業の成長を力強く後押しする、かけがえのない資産となるはずです。
「オワコン」という言葉に惑わされず、自信を持って、あなたのメディアを育てていってください。
もし、オウンドメディアの立ち上げや運用でお困りのことがあれば、いつでもご相談ください。
最初の相談は無料で承っています。
一緒に、最高のメディアを作り上げていきましょう。